
 | |||||||

KwMap.com - browse Keyword Map of the Internet |
����̊��o���f�ڂ��Ă���܂��B�����Ƀ����N�W�Ƃ��Ă��@�\���Ă��܂��̂ŕ����Ă���������Ǝv���܂��B�����N��͓��{��̃T�C�g���w�ǂł����A�ꕔ�C�O�̃T�C�g���݂��Ă��܂��̂Ŗ|�K�v�ȏꍇ�͍����j���[�̃I�����C���|��T�C�g�������p�������B�L���r���ɂȂ邱�Ƃ������̂ł������炸�B�܂��A�h�̂͏ȗ������Ē����Ă���܂��B 2003�N/ 3��/ 4��/ 5��/ 6��/ 7��/ 8��/ 9��/ �����`�A�[�m�E�x���I���A77�Ŏ��� 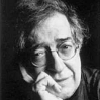 �����m�����̂����C�^���A�̍�ȉƃ��`�A�[�m�E�x���I����5��27���Ƀ��[�}�̕a�@�ŖS���Ȃ��Ă����炵���B
�x���I���͌���I�ȈӖ��ł̔����L���ȃA�C�f�A�̐�������Ă���A�Ⴆ�قړ�����̓����C�^���A��
�O�q��ȉƃ��C�W�E�m�[�m�͌������֗~�I�ȍ�ȕ��@�ɂ���ē��I�ȏW���ɂ��ٔ��������̃h���}��Nj�����X����
�������Ƃ���Ȃ�A�x���I���͑��ʂŔ����͖L���ȃ^�C�v�̍�ȉƂł����āA���y�ɂȂ��邠����v�f���������邱�Ƃɂ��A
�y�Ȃ������I�ȃh���}�ɂ܂Ŕ��W�����邱�Ƃɂ��o�����l�ȋC������B�G�����܂������肾���A
������������v�f����������p���͌��K���������Ă��������ȁB�ƁB
�����m�����̂����C�^���A�̍�ȉƃ��`�A�[�m�E�x���I����5��27���Ƀ��[�}�̕a�@�ŖS���Ȃ��Ă����炵���B
�x���I���͌���I�ȈӖ��ł̔����L���ȃA�C�f�A�̐�������Ă���A�Ⴆ�قړ�����̓����C�^���A��
�O�q��ȉƃ��C�W�E�m�[�m�͌������֗~�I�ȍ�ȕ��@�ɂ���ē��I�ȏW���ɂ��ٔ��������̃h���}��Nj�����X����
�������Ƃ���Ȃ�A�x���I���͑��ʂŔ����͖L���ȃ^�C�v�̍�ȉƂł����āA���y�ɂȂ��邠����v�f���������邱�Ƃɂ��A
�y�Ȃ������I�ȃh���}�ɂ܂Ŕ��W�����邱�Ƃɂ��o�����l�ȋC������B�G�����܂������肾���A
������������v�f����������p���͌��K���������Ă��������ȁB�ƁB
���u�G��(����)���܂����v�̌ꌹ  �����ŏ����Ƃ��āu�G�����܂����v�̌ꌹ���C�}�C�`�͂߂Ȃ������̂ł������ƒ��ׂĂ݂���A
�ǂ�Ŏ��̔@���w�G(���炷)����(����)�ɏW�܂��Ė������ɃK���K�������Ă���l�q�x�炵���B
�ōX�ɒ��ב�����Ɓw���̎���Ɋ������͂܂��������́A�k�q�]�̂�����ɏW�܂��Ă���A
����ɏ[���ȓW�J�������Ă��Ȃ����̓���l�͒������̐l�������猩��A�K���K���₩�܂����A���Œ����̐l�����͓���l���A
�u�G��(����)�v�ƌĂB���̌�A�ޗǁE�������ɂ��̌��t�����{�ɓ����Ă���ƁA���{�ɂ́u�G�����܂����v�Ƃ������Ƃ��ł��A
�����Ď������ɓ����Ă���͂��́u�G�����܂����v�́u����(����)���܂����v�Ƃ����A�e���ŏ����悤�ɂ��Ȃ����B�x�Ƃ����̂��B
�Ȃ�قǂȂ�قǁB
�����ŏ����Ƃ��āu�G�����܂����v�̌ꌹ���C�}�C�`�͂߂Ȃ������̂ł������ƒ��ׂĂ݂���A
�ǂ�Ŏ��̔@���w�G(���炷)����(����)�ɏW�܂��Ė������ɃK���K�������Ă���l�q�x�炵���B
�ōX�ɒ��ב�����Ɓw���̎���Ɋ������͂܂��������́A�k�q�]�̂�����ɏW�܂��Ă���A
����ɏ[���ȓW�J�������Ă��Ȃ����̓���l�͒������̐l�������猩��A�K���K���₩�܂����A���Œ����̐l�����͓���l���A
�u�G��(����)�v�ƌĂB���̌�A�ޗǁE�������ɂ��̌��t�����{�ɓ����Ă���ƁA���{�ɂ́u�G�����܂����v�Ƃ������Ƃ��ł��A
�����Ď������ɓ����Ă���͂��́u�G�����܂����v�́u����(����)���܂����v�Ƃ����A�e���ŏ����悤�ɂ��Ȃ����B�x�Ƃ����̂��B
�Ȃ�قǂȂ�قǁB
��Mozilla5.0�ɂ�����CSS�̃o�O  Mozilla5.0�n�Łuoverflow:auto;�v�uoverflow:scloll;�v�̓��������������̂ŁA���ׂĂ݂���C�C�T�C�g���݂����B
��͂�o�O�炵���B�����orverflow���g�p����͔̂����������悳�������B�����ʂ̕��@�ʼn������Ƃ��܂����B
Mozilla5.0�n�Łuoverflow:auto;�v�uoverflow:scloll;�v�̓��������������̂ŁA���ׂĂ݂���C�C�T�C�g���݂����B
��͂�o�O�炵���B�����orverflow���g�p����͔̂����������悳�������B�����ʂ̕��@�ʼn������Ƃ��܂����B
�EMozilla5.0�ɂ�����CSS�̃o�O�Fhttp://cssbug.at.infoseek.co.jp/detail/mozilla.html ���f�W�^���E�C���[�W  �d����gettyimages.com�ȂǂŃf�W�^���E�C���[�W�����鎖��������ł����A���̓x�Ɂu�Ȃ�ł���Ȃɍ����낤���H�v�Ǝv���̂ł��B
�����g������̂����C���[�W�͑����Ă邯�Ljꖇ40�h���͑Ղ��Ȃ���(���C�Z���X�`�Ԃɂ���肯��)�B�Ȃ̂ŁA
�����ł̓g�b�v�y�[�W�̃L�[���B�W���A���p�Ɉꖇ�����āA���̃C���[�W�͈��オ��ȃp�b�P�[�W�����g����
DAJ�Ȃǎg�������邵���Ȃ̂ł���B�ł�gettyimages.com�Ŏ������Photodisc�AImage Bank�Ȃǂ�
�������f�ތ��{��10���ȏ㑗���Ă���̂͊������B���܂���CD-ROM�������t���ė��Ă�����Ƃ���
�f�U�C���E�I�t�B�X�Ȃ���ׂƂ������ł��n�b�^���̏�����ɂȂ�B
���A�����₱�̑f�ތ��{�̂������ňꖇ�̒P�����オ���Ă�̂��낤���H���₢�₻��ȊȒP�Șb�ł�����܂��B
�ŁA������Čl�ŗ���ł������Ă����̂��ȁH�B������������ˁB
�d����gettyimages.com�ȂǂŃf�W�^���E�C���[�W�����鎖��������ł����A���̓x�Ɂu�Ȃ�ł���Ȃɍ����낤���H�v�Ǝv���̂ł��B
�����g������̂����C���[�W�͑����Ă邯�Ljꖇ40�h���͑Ղ��Ȃ���(���C�Z���X�`�Ԃɂ���肯��)�B�Ȃ̂ŁA
�����ł̓g�b�v�y�[�W�̃L�[���B�W���A���p�Ɉꖇ�����āA���̃C���[�W�͈��オ��ȃp�b�P�[�W�����g����
DAJ�Ȃǎg�������邵���Ȃ̂ł���B�ł�gettyimages.com�Ŏ������Photodisc�AImage Bank�Ȃǂ�
�������f�ތ��{��10���ȏ㑗���Ă���̂͊������B���܂���CD-ROM�������t���ė��Ă�����Ƃ���
�f�U�C���E�I�t�B�X�Ȃ���ׂƂ������ł��n�b�^���̏�����ɂȂ�B
���A�����₱�̑f�ތ��{�̂������ňꖇ�̒P�����オ���Ă�̂��낤���H���₢�₻��ȊȒP�Șb�ł�����܂��B
�ŁA������Čl�ŗ���ł������Ă����̂��ȁH�B������������ˁB
���V�hUNION�ɂ�  ���`�A�[�m�E�x���I�A�u���b�h�E�V���s�b�N�A������Winter & Winter����łĂ�悭�킩��Ȃ�
�A�R�[�f�B�I���t�҃X�e�B�A���E�J�V���e���Z����CD�����ꂼ��w���B���̃X�e�B�A���E�J�V���e���Z�����C�C�I
�t���[�W���Y�o���h���Ǝv���o���J����������Ƀu���K���A���E�{�C�X�A�^�u���̃��Y���A
������̉ʂĂɂ͒������ۂ���ȃR�[���X�܂Ŕj�V�r�ɂ��Ȃ��Ă܂��B
���ꂪ�܂��▭�ł��炵���̂ł��B
���`�A�[�m�E�x���I�A�u���b�h�E�V���s�b�N�A������Winter & Winter����łĂ�悭�킩��Ȃ�
�A�R�[�f�B�I���t�҃X�e�B�A���E�J�V���e���Z����CD�����ꂼ��w���B���̃X�e�B�A���E�J�V���e���Z�����C�C�I
�t���[�W���Y�o���h���Ǝv���o���J����������Ƀu���K���A���E�{�C�X�A�^�u���̃��Y���A
������̉ʂĂɂ͒������ۂ���ȃR�[���X�܂Ŕj�V�r�ɂ��Ȃ��Ă܂��B
���ꂪ�܂��▭�ł��炵���̂ł��B
��Max/MSP�ƃ��J�� 5���O�̏o�����B���J�����Ǝv������S�L�v�������B5���قNJi�����A���̂܂܂��ʂꂵ���B�C����蒼���āA�ēxMax MSP�Ɍ������B���͂₢���̕��i�B ��Max/MSP�ƃC���C�U�[  ������PowerBookG3�Ɍ�������10/7(��)�̃��C�u�ׂ̈�NanoPiano�������Ƃ����������t�p�b�`���V�N�V�N����B����ɔ]�݂�����ꂽ�̂�TV�𒅂���ƁA
����B�m����₱�ƃV���������́u�C���C�U�[�v���������������B�Ȃɂ��B�����A���͖��ނ̃V�����t���[�N�B
����������Ȃ��낤�B�ł�����͖ʔ����Ȃ��B
�ł��V�����t���[�N�Ƃ��Ă͌�������ɂ������Ȃ��B
�ł͉��̖ʔ����Ȃ��ƌ�����̂��H���̂Ȃ�A
������PowerBookG3�Ɍ�������10/7(��)�̃��C�u�ׂ̈�NanoPiano�������Ƃ����������t�p�b�`���V�N�V�N����B����ɔ]�݂�����ꂽ�̂�TV�𒅂���ƁA
����B�m����₱�ƃV���������́u�C���C�U�[�v���������������B�Ȃɂ��B�����A���͖��ނ̃V�����t���[�N�B
����������Ȃ��낤�B�ł�����͖ʔ����Ȃ��B
�ł��V�����t���[�N�Ƃ��Ă͌�������ɂ������Ȃ��B
�ł͉��̖ʔ����Ȃ��ƌ�����̂��H���̂Ȃ�A�V���������͋����ł͂����Ȃ��B�����Ď�����Ȃ�����B �V���������͔��߂𒅂Ă͂����Ȃ��B�����Ď�����Ȃ�����B �V����������PC��G���Ă͂����Ȃ��B�����Ď�����Ȃ�����B �ȏ�A �}�b�`���{�f�B�[�̂̐��A�Ȍセ�ꂾ���͎̂��o���č�������đՂ������B���łɌ����Ȃ�A�}�b�`���Ȃ��Ȃ��͂���ς�u�R�i���E�U�E�O���[�g�v���n�}����ˁB�{���o�[�^���҂��Ă��B�ƁA������ŃV�����ɘl�тēxMax/MSP�Ɍ������B ���g�ъD�M���E�� �V�h�䉑���Ԃ�Ԃ炵�Ă����炨�����Ȍg�ъD�M���E�����B �G�݉��ł悭��������q���̂����唻�Ă��݂����Ȃ�B �M���M�����Ă�B �����̒a�����ł��舢���O�̖����ł���B 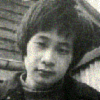 1978�N9��9���ނ͖S���Ȃ����B
���̍�����1�Ɣ����A������Ƃ�������������߂������B
���͉��ł��������Ȃ��ށB
�����A����ŏ\�����Ƃ��v���B
����ȏ�͖����A����ȉ����Ȃ��̂�����B
1978�N9��9���ނ͖S���Ȃ����B
���̍�����1�Ɣ����A������Ƃ�������������߂������B
���͉��ł��������Ȃ��ށB
�����A����ŏ\�����Ƃ��v���B
����ȏ�͖����A����ȉ����Ȃ��̂�����B
���ߑ��f�U�C�i�[�A���_�G�~����  �f��u�p�Y�v�̈ߑ��A�����ȂƎv�����烏�_�G�~����ł����B�܂����ꂽ�`���Ċ����ł��B
���̕��A���ɂ����C�x���E�`�����ēu�v�Ƃ̎O�o���v��s�[�^�[�E�O���[�i�E�F�C��i�A
�����i�A�܂��O�֖��G����̕���u�є�̃}���[�v�O���[�i�E�F�C�̃I�y���u�t�F�����[���̎莆�v���A
���̈��|�I�ȐF�ʊ��o�ɖ��x��������܂��B���{�l�̑@�ׂȊ��o�Ƃ����̂͂�͂萦�����̂ł��B
���̃I�y���w�t�F�����[���̎莆�x�͉��o���O���[�i�E�F�C�A�ߑ������_�G�~����A
���y���A���h�����[�Z���Ƃ������ȃR���{���[�V�����ł���B�ĉ����Ă���Ȃ����Ȃ��B
�f��u�p�Y�v�̈ߑ��A�����ȂƎv�����烏�_�G�~����ł����B�܂����ꂽ�`���Ċ����ł��B
���̕��A���ɂ����C�x���E�`�����ēu�v�Ƃ̎O�o���v��s�[�^�[�E�O���[�i�E�F�C��i�A
�����i�A�܂��O�֖��G����̕���u�є�̃}���[�v�O���[�i�E�F�C�̃I�y���u�t�F�����[���̎莆�v���A
���̈��|�I�ȐF�ʊ��o�ɖ��x��������܂��B���{�l�̑@�ׂȊ��o�Ƃ����̂͂�͂萦�����̂ł��B
���̃I�y���w�t�F�����[���̎莆�x�͉��o���O���[�i�E�F�C�A�ߑ������_�G�~����A
���y���A���h�����[�Z���Ƃ������ȃR���{���[�V�����ł���B�ĉ����Ă���Ȃ����Ȃ��B
�E���_�G�~�Fhttp://www.kiryu.co.jp/wadaemi/ ���v�X�̓����^���[  �v�X�ɓ����^���[���ɍ݂�W���[�}���E���b�N�̐��n�u�R�Y�~�b�N�E�W���[�J�[�Y�v�Ɍ������B
�A�����E�f���[�����A���E�m�C�I�A�|�|���E���[�A�N���E�X�E�f�B���K�[�̃\���Ȃǂ̌@��o�����͖������Ƌ����Ă݂����A
�u���Ă�������(CD)�͂قƂ�ǎ����Ă���̂ŁA�����������͂Ȃ������B������Ǝc�O�B
���ƁA�����͂قڑS�������o����̂������̂ł��B
�v�X�ɓ����^���[���ɍ݂�W���[�}���E���b�N�̐��n�u�R�Y�~�b�N�E�W���[�J�[�Y�v�Ɍ������B
�A�����E�f���[�����A���E�m�C�I�A�|�|���E���[�A�N���E�X�E�f�B���K�[�̃\���Ȃǂ̌@��o�����͖������Ƌ����Ă݂����A
�u���Ă�������(CD)�͂قƂ�ǎ����Ă���̂ŁA�����������͂Ȃ������B������Ǝc�O�B
���ƁA�����͂قڑS�������o����̂������̂ł��B
���W���[�}���E���b�N�ɑ���l�I�ȏd�v��  �������ł̓A�����E�f���[���́wAirs on a Shoestring (Best of...)�x��3�ȖڂɎ��^����Ă���uOne Moments Anger is Two Pints of Blood�v������Ă���B
�S�̓I�Ɍ����Ė��邢�g�[���ł͖���12�����ɋy�Ԃ��̋Ȃ͖l�ɂƂ��ĂƂĂ��d�v�ȃE�F�C�g���߂Ă���B
���̗��R��������ΐ肪�����̂����ے�I�Ȍ������狓����ƁA
�܂��l�͑��Ɍ����f�B�X�g�[�V�������������M�^�[�̉��F�����܂�D���ł͂Ȃ��B
�܂肻�̎�@�����܂�ɂ����ՂȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂��B
�����M�^�[�𑀂鏔�q�͂��̎�̉��̓W�~�w���ŋɂ݂ɒB���Ă��鎖�ɋC�Â��Ă��Ȃ���A
����A�C�t���Ă��邪�̂ɁA������O�̉��Ƃ��ĐZ���d���Ă��邪�̂ɁA���Ղɂ��̕��@�ɐg��C���邵�������̂�������Ȃ��B
�������A����͂ƂĂ��댯�Ȏ��ł���B�Ȃ��Ȃ炻���ň�̃N���G�[�V������j�����Ă���ɑ��Ȃ�Ȃ����炾�B
�V�����Ȃł���A�V�������ł���A�^����n�����悤�Ƃ���̂ł���A�{�����̃f�B�X�g�[�V�����E�T�E���h�������{���猩�����čs���ׂ��ł͂Ȃ��̂��H
�������ł̓A�����E�f���[���́wAirs on a Shoestring (Best of...)�x��3�ȖڂɎ��^����Ă���uOne Moments Anger is Two Pints of Blood�v������Ă���B
�S�̓I�Ɍ����Ė��邢�g�[���ł͖���12�����ɋy�Ԃ��̋Ȃ͖l�ɂƂ��ĂƂĂ��d�v�ȃE�F�C�g���߂Ă���B
���̗��R��������ΐ肪�����̂����ے�I�Ȍ������狓����ƁA
�܂��l�͑��Ɍ����f�B�X�g�[�V�������������M�^�[�̉��F�����܂�D���ł͂Ȃ��B
�܂肻�̎�@�����܂�ɂ����ՂȋC�����ĂȂ�Ȃ��̂��B
�����M�^�[�𑀂鏔�q�͂��̎�̉��̓W�~�w���ŋɂ݂ɒB���Ă��鎖�ɋC�Â��Ă��Ȃ���A
����A�C�t���Ă��邪�̂ɁA������O�̉��Ƃ��ĐZ���d���Ă��邪�̂ɁA���Ղɂ��̕��@�ɐg��C���邵�������̂�������Ȃ��B
�������A����͂ƂĂ��댯�Ȏ��ł���B�Ȃ��Ȃ炻���ň�̃N���G�[�V������j�����Ă���ɑ��Ȃ�Ȃ����炾�B
�V�����Ȃł���A�V�������ł���A�^����n�����悤�Ƃ���̂ł���A�{�����̃f�B�X�g�[�V�����E�T�E���h�������{���猩�����čs���ׂ��ł͂Ȃ��̂��H�b��߂��Ɩl���W���[�}���E���b�N���D�ނ̂͂����������_�Ōl�l�̃��`�x�[�V�����������C������̂��B �����̂���ƃ~���[�W�V�����̑�}(�����悻)�����㉹�y����e��������A�������̓C���X�p�C�A����Ă��鎞�_�ő傫���ًɉ�����̂��낤���A ����ɂ��Ă��F�~�S�̃��b�N�E�~���[�W�V�����Ŗ������Ƃ͉����킩�邵�A�����͂�����B �X�ɑ�����ƁA�l�̏ꍇ�̃N���G�[�V�����Ƃ͂����������ʂɃ|�b�v�X���D�ސl�ɂ��������y�Ԕ͈͂Œ��Ȃ���ΈӖ��������ƍl���Ă���B ���@�_���肫�̉��y�͂��͂≹�y�ł͂Ȃ��B�܂艹���y���ޑΏۂł͂Ȃ��Ƃ��������B ���@�_�����s������C���e���V����t�ł鉹�͉��̐����͂������Ȃ����A�����Ă���Ƃ������Ȃ��B �܂��A�ǂ��\�����𐂂�悤��������Ƃ��Ă͈�u�̉��߂ŏI����Ă��܂��B�S�ɂ͎c��Ȃ��̂��B �v�f�Ƃ��Ĕ��ɔ\���I�ɉ��y�ɎQ�������悤�Ƃ��Ă���̂�������Ȃ����Aꡂ��ɎI�ɐ��炴��Ȃ��y�Ȍ`�ԁB ����Ȃ͔̂g�`�̌����҂Ƃ��Ăł��������Ă����Ē��������B���܂��܉����������特�y������A�Ƃ����ʂ͎��߂đՂ������B ���ǁA���@�_��}�e���A���Ȃ�Ă�������ׂ邱�Ǝ��́u���y�v�̏�ł̓N�\�̖��ɂ������Ⴕ�Ȃ��̂�����B ���u�����e�o�� 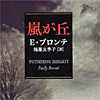 �ŋ߂܂��{�������Ă����̂Ŗ{�I�����Ă�����̓ǂV���[���b�g�E�u�����e�́u�W�F�[���E�G�A�v���o�Ă����B
���l�ł͂Ȃ��ǎ��̃q���C���ƃu�T�C�N�Ȓj�Ƃ̃��u�E���}���X�ƌ������܂�ɂ���O����тт������V�i���I��
�����̎����Ƃ��Ă͑S�������ċ����E�������o������e�ł͂Ȃ������B
�܂��A�G�~���[�E�u�����e�̌ÓT���w�u�����u�v�����l�Łu����l�͋��܂��˂��v�Ƃ���̂킩��Ȃ��|��Ԃ�ɂ��Q��Ȃ���ǂ��̗̂���s�\�B
�f����ς�Η����o�����Ȃ����ƃ��[�����X�E�I�����B�G���q�[�X�N���t�����������m�N���f��uWuthering Heights�i�����u�j�v���ς��̂����A
��͂蕪����Ȃ��B���̊��o�͉��Ȃ낤���B�p���ł͒��b���I�|�W�V�����ł���ƕ������z���g�ɂ����Ȃ̂��낤���H
���ǂ��ǂ남�ǂ낵�������W�̈������݂��I�J���g���Ƃ������ߏo���Ȃ��܂܍����Ɏ���B
����A�������{�I����o�Ă����h�X�g�G�t�X�L�[�u�n�����̎�L�v�A�J�t�J�u�ϐg�v�Ȃǂ͍��ǂ�ł������ɔ�����̂��낤�B
�����͂�����ēǂ��Ă݂悤���Ǝv���B
�ŋ߂܂��{�������Ă����̂Ŗ{�I�����Ă�����̓ǂV���[���b�g�E�u�����e�́u�W�F�[���E�G�A�v���o�Ă����B
���l�ł͂Ȃ��ǎ��̃q���C���ƃu�T�C�N�Ȓj�Ƃ̃��u�E���}���X�ƌ������܂�ɂ���O����тт������V�i���I��
�����̎����Ƃ��Ă͑S�������ċ����E�������o������e�ł͂Ȃ������B
�܂��A�G�~���[�E�u�����e�̌ÓT���w�u�����u�v�����l�Łu����l�͋��܂��˂��v�Ƃ���̂킩��Ȃ��|��Ԃ�ɂ��Q��Ȃ���ǂ��̗̂���s�\�B
�f����ς�Η����o�����Ȃ����ƃ��[�����X�E�I�����B�G���q�[�X�N���t�����������m�N���f��uWuthering Heights�i�����u�j�v���ς��̂����A
��͂蕪����Ȃ��B���̊��o�͉��Ȃ낤���B�p���ł͒��b���I�|�W�V�����ł���ƕ������z���g�ɂ����Ȃ̂��낤���H
���ǂ��ǂ남�ǂ낵�������W�̈������݂��I�J���g���Ƃ������ߏo���Ȃ��܂܍����Ɏ���B
����A�������{�I����o�Ă����h�X�g�G�t�X�L�[�u�n�����̎�L�v�A�J�t�J�u�ϐg�v�Ȃǂ͍��ǂ�ł������ɔ�����̂��낤�B
�����͂�����ēǂ��Ă݂悤���Ǝv���B
�����Y���̖{�� / L�E�N���[�Q�X  ����̖{�I�����̂Â��ŏo�Ă����{�w���Y���̖{���x�B
����̓h�C�c�̐��̓N�w�҃��[�h���B�q�E �N���[�Q�X�ɂ��u���Y���v�Ɖ]�����`�I�Ȍ��t�ɕz�𓊂������ŁA
���g���̎��R�I�Ȃ��̂���l�דI�����ɂ�鉹�y�A�G�悻���ĕ��w���X�ɂ����锽���Ȃ������̖��ɂ��ċL�q����Ă���B
������u���̓N�w�v�Ƃ�������Ɋ܂܂����e�ɂȂ�̂�������Ȃ����A�h�C�c�_���`���n�̗�I�Փ����S�J�̓��e�ł�����B
����̖{�I�����̂Â��ŏo�Ă����{�w���Y���̖{���x�B
����̓h�C�c�̐��̓N�w�҃��[�h���B�q�E �N���[�Q�X�ɂ��u���Y���v�Ɖ]�����`�I�Ȍ��t�ɕz�𓊂������ŁA
���g���̎��R�I�Ȃ��̂���l�דI�����ɂ�鉹�y�A�G�悻���ĕ��w���X�ɂ����锽���Ȃ������̖��ɂ��ċL�q����Ă���B
������u���̓N�w�v�Ƃ�������Ɋ܂܂����e�ɂȂ�̂�������Ȃ����A�h�C�c�_���`���n�̗�I�Փ����S�J�̓��e�ł�����B�K���I�ɍ��܂ꂽ���q�͎�e�҂��o�����������S�n�ɂ�����B ����ƈӎ��Ɩ��ӎ����Η�����悤�ɁA���q�ƃ��Y���͑Η��W�ɂ��邱�ƂɂȂ�B �Η��W�Ƃ́A���Y�������_��p�̐��ݏo�����q�Ɏx�z�����ƁA ����ɂ���ă��Y���͐����͂����������Ă��܂��Ƃ������Ƃł���B �����ʂ����ă��Y���Ɣ��q�Ƃ̊W�́A���̂悤�ȒP���Ȃ��̂Ȃ̂��낤���H�B �d�Ԃɗh���Ă���Ƃ��A�@�B�I�Ȕ��q�������X�ƒ����Ă���̂ɂ�������炸 �S�n�悭�����Ɩ���ɗU�����Ԃ͒N�������̌����Ă��邱�Ƃ��낤�B ���̏ꍇ�A�N���[�Q�X�ɂ��K�^���S�g���Ƃ����ԗւ�����������̔��q�ƐU�����A ��e�҂ɂ���Ď����I�ɕω����郊�Y���ɒu���������A ���܂��ɉ^��Ă���Ƃ������o��̌��������Ɉ��g�������������̂ł���B �܂��A�Ԃ�V�̗h���Ă�h�炷�Ƃ��ɁA ����̑����瑼���̑��ֈڍs����]���_�ň�u�~�߁A ���̂��Ƃɂ���Đ�ڂ������q������������Ԃ�V�͂������Q�ĂȂǂ����Ȃ����낤�B �h�肩���ŏd�v�Ȃ̂͂��������I��Ȃ������Ă��邩�̂悤�ȗ�����Ԃ����o�����Ƃł���A ���̂��߂̎�i�Ƃ��Č݂��ɔ��Ε������������߂������������I�ω����K�v�Ȃ̂ł���B �t�������Ď��I�Ȍ������Ȍ��ɉ]���ƁA ���i���I�ȁu���̐U���E���E�����v�͂�����v�f�ɂ����g���ƕs�����A�s������180�x�t�]������̂ł�����ƍl������B ���̗v�f�̈�Ƃ��ċ�������̂͂��̍s�ׂ��u�\���I���I���v�ł���B �����h�����ʂΑ��ɉ^�сA�S�ĉ^�яI���₢�Ȃ⍡�x�͌��̑��ɖ߂� (�ȉ����X�J��Ԃ�) �Ƃ������₪���邪�A ���̔\���I�s�� (���m�ɂ͔��\���I�s��) �́u���Ӗ��v���̂��̂�̌�����A�����́A�̌������邱�Ƃɑ��Ȃ疳���B �u���Ӗ��v�Ȃ��̂Ɋւ��Đl�Ԃ͕s�����������A����ɕs�����ɋ���A�ŏI�I�ɂ͋�ɈȊO�̉����m�ł������Ȃ�B �E�s���� �� �s���� �� ��� �� �v�l��H�̕��f���A�Ƃ�������ł���B ����A��o�̓d�Ԃ�h���Ă̗�������ł��邪�A �I�ȍs�ׂɂȂ�Ɠr���o�߂͈�]����B �I�ň���ȏ�A���̐��͔���Ȃ��������邪�A�����i�K�ɒu���Ă̕s�����͈�l�ł�����B �ɂ��ւ�炸�A���̒i�K�ɓ�����s�����̕����������ɒu�������\���͋ɂ߂č����B �������́A���̉������z���Ĉ�C�Ɏv�l��H�̕��f�Ɍ��т������l������B �E�s���� �� �v�l��H�̕��f���A�Ƃ�������ł���B �ǂ���ɂ���u���̐U���E���E�����v�͍ŏI�I�Ɏv�l��H�̕��f�����������Ƃɂ͕ς햳���A�������s����͓����Ȃ̂�������Ȃ��B ���N�����l�b�g�̌l�I�Ȏg���� / ����  ���͎����̉��t�ɂ����ăN�����l�b�g�̐�߂銄���͔��ɑ傫���B
���Ƀ\���̏ꍇ�̓N�����l�b�g�̎���{�I�ȓ����Ƃ͕ʂ́u�����v�������o�����t
�𑱂��Ă��������ƍl���Ă���B
���݂͂��ׂ̈̈�̕��@�Ƃ���PowerBook���g�p���Ă�����A
�ł́A�����������̃N�����l�b�g������{�I�ȓ����Ƃ͉��������炽�߂čl���Ă݂����B
�܂��A�V���O�����[�h�̖؊NJy��ł���N�����l�b�g�͌��ĕ�����ʂ�~���`�ł���
�o�X��A���g�ȂǑ召�ǂ̂悤�ȃT�C�Y�̕��ł����Ă�����͓����ł���B
�~���`�̏ꍇ�I�[�o�[�u���[�����ۂɉ~���`�̃T�b�N�X���Ƃ͈Ⴂ12�x�A
�܂�I�N�^�[�u+5�x (��1) ���o�������B
�����čX�ɃN�����l�b�g�͌��݂̊NJy��̒��ł͗B��̕ǎ� (��2) �̊y��u�ǃp�C�v�v�ł���ׁA
�I���K�����Ɠ��l�A������������̉~���`�y��������悻1�I�N�^�[���Ⴍ�Ȃ�B
�����̎����瑼�̃��[�h�y��(�T�b�N�X��) ��t���[�g�ɔ�ׁA���|�I�ɍL��������J�o�[�ł����ł��B
���ƈ�A�N�����l�b�g�͊�{�����o�Ȃ��Ƃ������̊y��ɂ͌����Ȃ��Ɠ��̔{���g�D�������Ă��܂��B
�����ʼn]������ / ��Ƃ͔g���́u�R(��)�v�Ɓu�J(��)�v�̎��Ő��l�I�ɂɂ܂Ƃ߂Ă݂��
���͎����̉��t�ɂ����ăN�����l�b�g�̐�߂銄���͔��ɑ傫���B
���Ƀ\���̏ꍇ�̓N�����l�b�g�̎���{�I�ȓ����Ƃ͕ʂ́u�����v�������o�����t
�𑱂��Ă��������ƍl���Ă���B
���݂͂��ׂ̈̈�̕��@�Ƃ���PowerBook���g�p���Ă�����A
�ł́A�����������̃N�����l�b�g������{�I�ȓ����Ƃ͉��������炽�߂čl���Ă݂����B
�܂��A�V���O�����[�h�̖؊NJy��ł���N�����l�b�g�͌��ĕ�����ʂ�~���`�ł���
�o�X��A���g�ȂǑ召�ǂ̂悤�ȃT�C�Y�̕��ł����Ă�����͓����ł���B
�~���`�̏ꍇ�I�[�o�[�u���[�����ۂɉ~���`�̃T�b�N�X���Ƃ͈Ⴂ12�x�A
�܂�I�N�^�[�u+5�x (��1) ���o�������B
�����čX�ɃN�����l�b�g�͌��݂̊NJy��̒��ł͗B��̕ǎ� (��2) �̊y��u�ǃp�C�v�v�ł���ׁA
�I���K�����Ɠ��l�A������������̉~���`�y��������悻1�I�N�^�[���Ⴍ�Ȃ�B
�����̎����瑼�̃��[�h�y��(�T�b�N�X��) ��t���[�g�ɔ�ׁA���|�I�ɍL��������J�o�[�ł����ł��B
���ƈ�A�N�����l�b�g�͊�{�����o�Ȃ��Ƃ������̊y��ɂ͌����Ȃ��Ɠ��̔{���g�D�������Ă��܂��B
�����ʼn]������ / ��Ƃ͔g���́u�R(��)�v�Ɓu�J(��)�v�̎��Ő��l�I�ɂɂ܂Ƃ߂Ă݂�����J�NJy��̏ꍇ (�T�b�N�X�ȂǁA�w��) �@�J�ǎ��̊y��́A�ǂ̗��[�̋�C�k�����傫���A�g���͊ǂ̒����́u2�{�v�ł��邱�Ƃ���A �@�E��͔g����1/2 (0.5 �~��1��k) �@�E��2�{���͔g����2/2 (1.0 �~��2��k�A��2�~��2����1) �@�E��3�{���͔g����3/2 (1.5 �~��3��k�A��3�~��3����1) �@�E��4�{���͔g����4/4 (2.0 �~��4��k�A��4�~��4����1) �@�E��5�{���͔g����5/2 (2.5 �~��5��k�A��5�~��5����1) ���NJy��̏ꍇ (�N�����l�b�g) �@�ǎ��̊y��́A�ǂ̕Е��̋�C�k�����ł��傫���A�g���͊ǂ̒����́u4�{�v�ł��邱�Ƃ���A �@�E��͔g����1/4 (0.25 �~��1��k) �@�E��3�{���͔g����3/4 (0.75 �~��2��k�A��3�~��3����1) �@�E��5�{���͔g����5/4 (1.25 �~��3��k�A��5�~��5����1) �@�E��7�{���͔g����7/4 (1.75 �~��4��k�A��7�~��7����1) �@�E��9�{���͔g����9/4 (2.25 �~��5��k�A��9�~��9����1) �ɁF�g�� / �g���P��U������ۂɐi�ދ���(�P�ʂ� m�F���[�g��) �ˁF�U����(���g��) / �P�b�Ԃɔg���U�������(�P�ʂ� 1/s �������� Hz�F�w���c) ���F���� / ���̑��x(�P�ʂ� m/s)�B�P�b�Ԃɉ��g���i�ދ����ƍl���Ă��悢�B ���F�ǂ̒��� �ƂȂ�܂��B ��1) �N���B���e�B�[�����F�I�[���@�[�u���[��12�x�A�܂�̓I�N�^�[�u + 5�x��ɂȂ邱�� �I�N�^�[���B�[�����F�I�[���@�[�u���[���I�N�^�[����ɂȂ邱�� ��2) �ǂ̈�����ǂ���Ă���NJy��̂��Ƃł����A�����ł����ǎ��Ƃ́A �������́u�ǎ��̉��k���𗘗p�����NJy��v�Ƃ������Ƃł��B �ǎ��̊y��́A�ǂ̕Е��̋�C�k�����ł��傫���A�g���͊ǂ̒�����4�{�ł��B �N�����l�b�g�ȊO�̂يNJy��͂Ƃ�NJJ�ǎ��ŁA �����͊ǂ̗��[�̋�C�k�����傫���A�g���͊ǂ̒�����2�{�ł��B ���N�����l�b�g�̌l�I�Ȏg���� / ���t���@  �N�����l�b�g�̂����̓����܂�����ŁA
�l�͌��݁A�������s���Ă���u���b�v�g�b�v(PowerBookG3) + �y��v�Ƃ����\�����̂��Ċ������Ă܂��A
�������A���b�v�g�b�v�E�R���s���[�^���g���̂͏�L�ɋ������u��{�I�ȓ����v��ʂ̓����A
�����Ắu�����̒i�K�v�ւƊg��������ׂ̕��@�A�܂��͊��o�ł��������A
�L�`�ł̓N�����l�b�g���g�����g�[���E�}�e���A�� (�����̕��̍\���v�f�A�f��) �̒Njy�ɉ߂��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
����ɂ͈�ʂɓ`������t�@ (�d���t�@�A�z�ċz��) �ł͂Ȃ��A
���A���@���M�����h�ȑt�@ (�S���z�[�X���������ށA�x��������z�����ށA�}�E�X�s�[�X���ĊǑ̂����Ő����A�}�E�X�s�[�X�����Ő�����)�ł������ʂȕ��@��
�u�����̒i�K�v�ւƊg�������čs�������̂ł��B
�N�����l�b�g�̂����̓����܂�����ŁA
�l�͌��݁A�������s���Ă���u���b�v�g�b�v(PowerBookG3) + �y��v�Ƃ����\�����̂��Ċ������Ă܂��A
�������A���b�v�g�b�v�E�R���s���[�^���g���̂͏�L�ɋ������u��{�I�ȓ����v��ʂ̓����A
�����Ắu�����̒i�K�v�ւƊg��������ׂ̕��@�A�܂��͊��o�ł��������A
�L�`�ł̓N�����l�b�g���g�����g�[���E�}�e���A�� (�����̕��̍\���v�f�A�f��) �̒Njy�ɉ߂��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
����ɂ͈�ʂɓ`������t�@ (�d���t�@�A�z�ċz��) �ł͂Ȃ��A
���A���@���M�����h�ȑt�@ (�S���z�[�X���������ށA�x��������z�����ށA�}�E�X�s�[�X���ĊǑ̂����Ő����A�}�E�X�s�[�X�����Ő�����)�ł������ʂȕ��@��
�u�����̒i�K�v�ւƊg�������čs�������̂ł��B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | Biography | Works | Audio | Photography | Sales | Contact |